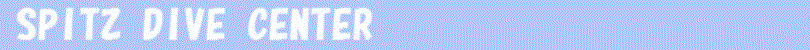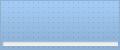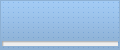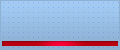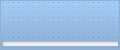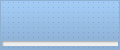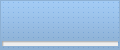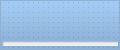���Q�O�O�X�^�P�P�����O�u�b�N
���P�P�^�R�O�@����@�C���@�Q�R���@�����@�Q�P�܂��͂Q�S���@�k���@�g���Q�D�T�l�@�����x�@�P�T�l
���̃C���t���G���U�����������܂�A�����ɕۈ牀�ɒʂ��n�߂Ă��ꂽ�̂Ŏ�������ɏo�����Ă��܂����B
�_���}�n�[���ƂĂ����킢���B�傫���̂��珬�����̂܂őS�����킢���̂��B���̖ڃ����Y�ł��B���Ă݂�����ǁA����ς��肫��Ȃ��̂��B

�n�i�q�Q�E�c�{�͈ꏏ�ɐ����Ă����ߔe�̂h����ɋ����Ă����������B�����鎞�Ԃ�ߖ�ł��܂����B���ӁB������͒��̖ڃ����Y�Ŋ���Ă݂܂����B

�ߌォ��͐�ɓ˓��B�����͍��N�A�ł��Ռ��I�ȏo������ꂽ�y������B�~�̗l�q�����Ă����˂E�E�E�Ǝv���A�����B�����͂Q�P�x�B�ӂނӂށB�i�����E�{�E�Y�n�[���ǔh��ɂȂ��Ă�������j���ł���B�Ă����Y�킾�B

�����C�{�E�Y�n�[���I�X�������B�Ȃ��E�E�E�A�Ă������₩���ȁE�E�E�B�Ȃ�ŁH

�����C�{�E�Y�n�[�̃��X����˒[��c���Ă��܂����B�Ȃɂ��������̂�������̂��낤���H�@�݂�ȂŏW�܂��āA��̉���`���Ă��܂����B

�^���g���n�[�ɂ��o��܂����B��̒�ɂ��܂��Ă����ԓy�����Ȃ��Ȃ��Ă��āA�B�e�ł��܂����B�Ă͂����ƔZ���ԓy���͐ς��Ă��āA�B�e�͕s�\�ł������A�����͊y���ł����B

�������A�^���g���n�[�̎q���������E�E�E�B���̋��A��Ŋ뜜�T�a�ނƂȂ��Ă���܂��B

�}�ӂŌ��Ă���ƃ����{�E�Y�n�[�̎q�����Ǝv���B���m�ɂ́E�E�E�A���̂ւ�͔��f���Ȃ��E�E�E�Ƃ����������Ȃ��B�܂��ɂȂƂ��ɗ�ؐ搶�Ɍ��Ă����������B

�i�����E�{�E�Y�n�[�̃��X�ł��傤�B����܂��������܂����B

�Ȃڋ߂��Ē��̖ڃ����Y�ŗV�т����E�E�E�Ǝv���Ă�����A�G�r�����B���Ă��āA��������V���Ă������������E�E�E�B

�܂��͂ǃA�b�v�B���[��E�E�E�E�B���ז��Ŕw�i�𐅂Ŕ����Ȃ��E�E�E�B


����ɂ��Ă��i�����E�{�E�Y�n�[�A�Ă����f�R�������B���A�b�v�ŎB���Ă��܂����B

�����C�{�E�Y�n�[���H�@���₢��A�Ⴄ���낤�B�J�G���n�[�H�@���₢��A�������������Ă��Ȃ���B�A�J�{�E�Y�n�[�H�@���[��E�E�E�A���̐��͔ے�ł��Ȃ��B�A�J�{�E�Y�n�[�̃��X��������Ȃ��B�������A�q���R�����{���X�n�[�������Ă̂͂ǂ���H�@�܂�Ȃ����Ƃ��Ȃ��B��ؐ搶�ɕ����Ă݂܂��ˁB

�E�i�M�̒��Ԃ��E�E�E�E�B����܂����O�͂킩��Ȃ��ȁ[�B

�O�b�s�[���������܂����B����܂Ă������������Ă���B

��C�A�S�R�B��Ȃ������̂Ŋy�ɎB��܂����B�W���F���E�E�E�A�����ȐF�������Ă����ł��ˁ[�B

�����C�{�E�Y�n�[�̃y�A�������̂ŎB���Ă��܂����B

�������A���̋G�߂̐�͉Ă����y�����ȁ[�B�������B
���P�P�^�Q�R�@�܂�̂����ꂽ�܂ɏ��J�@�C���@�Q�T���@�����@�Q�S�`�Q�T���@�k�����@�g���Q�D�T�l�@�����x�@�P�`�T�l
�A�x���Ƃ����̂ɁA�ƂĂ��ɂ��B�n���̂��q�l�ƌߌォ��Q�{�����Ă��܂����B�~�W��������_���Đ������̂����A�ߌ�͂��Ȃ��̂��E�E�E�E�B��U��ł����B�S�R���Ȃ������E�E�E�B
���߂ă}�N���I�����T���B�E�~�E�V�T������A�b�k�ނ�������E�E�E�B
�ʐ^�̓C�\�o�i���J�N���G�r�B�傫���̂������̂ŁA���̖ڃ����Y�Ŋ���Ă݂��B
���ɎB��Ȃ����E�E�E�B

�����o�Ă����E�E�E�B���N�قړ����G���A�Ō�����e�k�E�j�V�L�E�~�E�V�B�C���p�N�g�̂���`��Ȃ̂ŁA���q�l���ǂ������ł��B

���̖ڃ����Y�ł��q�l��w�i�ɓ���ĎB�e�B�̐S�̐����������Ă��܂��E�E�E�B

�N�����h�[���X�E�q���g�D�A�l���V�X�͐�������G���A�Ƃ͕ʂ̃G���A���甭���B

�����Ȋ����ŎB���Ă���̂����E�E�E�A���܂�y�������Ⴕ��ɂȂ�Ȃ����B

���ĂāA�������������イ�́E�E�E�Ǝ����ł��v���Ă��܂����B�q���g�D�A�l���V�X�̂R�A���B�X�g���{�̓��ĕ����|�C���g���ȁE�E�E�B

�A�J���n�[�̎q�������ꒅ�����悤�ł��B�~���z����̂��H�@�����͂Q�̂��܂����B

����ɔ�ׂāA�����͕q���ł����B�J�G���A�}�_�C�I�I�@�c�ʒu�ɂ��ă_�C�o�[�ƃW���[���E�E�E�E�Ƒ_���Ă݂���A�����悭�������Ă��܂��܂����B

�E�~�V���E�u�n�[�ł��傤���H�@�ŏ��A��ʍ��̌̂ɓ������āA���̖ڃ����Y�ł̎B�e�͒��߂��̂����A��C�ɂȂ����Ƃ�������Ă���ƑS�R�����Ȃ��B
����āA�g���}�N�b�e���܂����B�ł��A�Ȃ��Ȃ������̂��Ȃ���ł���ˁE�E�E�B

�A��ɂ̓^�c�m�n�g�R�������̂ŎB�e�B���傤�Ǘ������̎����Ȃ̂�������Ȃ��B���̌�A�ӂ�ӂ�Ɯp�j����ɏo�����܂����B

���炭�ɂȂ̂ŁA���Д�э��݂Ő���ɂ��ĉ������܂��B
��ѓ���劽�}�ł��B���Ђ����ł��������܂��B
���P�P�^�Q�Q�@�܂�̂����ꂽ�܂ɏ��J�@�C���@�Q�T���@�����@�Q�S�`�Q�T���@������k���@�g���Q�D�T�`�T�D�O�l�@�����x�@�P�`�T�l
�挎�V�тɗ��Ă������������q�l���Â��q��A��đ̌��_�C�r���O�����ɗ��Ă���܂����B�����ɂ��̓V��ƊC���ł������A���̓��̌ߑO���͂悭����Đ��������邩�����ł��B
�̌��̂��q�l�����͂ƂĂ��y�������ŁA���[������̃p���[���Č��Ă��邾���œ`����Ă���B
�_�C�r���O���X�^�[�g�����Ƃ����̂ɂȁ[�B

��r�I�A�����x�̗ǂ���Ԃʼnj�����Ƃ��J���܂����B
�E�V�m�V�^�̒��Ԃ�A�N�}�m�~�A�n�i�~�m�J�T�S�A�n���Z���{���ȂǏ��S�Ҏ������ȋ����������܂Ȃ��`�F�b�N�I�I
������Ԉ�ۂɂ̂����Ă���̂��낤���H
�̌��Ȃ̂ɂT�O�����炢�����Ă��܂����E�E�E�B
���P�P�^�Q�P�@�܂�̂����ꂽ�܂ɏ��J�@�C���@�Q�T���@�����@�Q�S�`�Q�T���@������k���@�g���Q�D�T�`�T�D�O�l�@�����x�@�P�`�T�l
�X�s�b�c�ɍŋ߈�ԗV�тɗ��Ă��������Ă���n���̃��s�[�^�[�̕��ƒ�����}���c�[�Ń_�C�r���O�B��������̍~�J���Ђǂ��������A���Ȃ�C�����������Ă���B
�R���f�B�V�����͑S�R�ʖڂ�����ǁA�|�C���g�̓����x�͂Ȃ��Ȃ��ǂ������B
�E�~�E�V�ł͐��邽�тɏo����Ă��܂��A�N�����h�[���X�E�q���g�D�A�l���V�X�B

�R�����E�~�E�V���o��B

�_���Ă������N�V�}�C���V�̌Q��ɂ������B������Ă��܂��܂����B

�J�X���n�[�̉��F�o�[�W�����͂������������܂��B

�V�}�I���n�[���Ȃ��Ȃ��B��Ȃ������̂ŁA�Ō�̍Ō�ɒ��̖ڃ����Y���g���ĎB���Ă�낤�ƍl���Ă����̂����A�Ȃ��Ȃ��n�[�͊�点�Ă���Ȃ��B

�ŋ߂悭����E�i�M�M���|�B
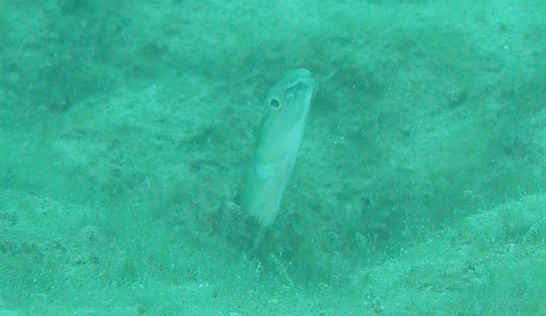
�J�G���A�}�_�C�͂���ς肩�킢���B�S�������Ă��܂��炵���E�E�E�B

���ʂŊ炾���B���Ă��y�����Ȃ��̂ŁA�Ȃ�Ƃ��p�x�����Ē��̖ڃ����Y�Ŋ���Ă݂��B���[��E�E�E�A�e���ł����ȁ[�B�Ȃ�Ƃ��Ώ����Ă����Ȃ��ƁE�E�E�B

�g�K�����G�r�r�o�͂�����Ƒ�_�ɎB��܂����B

�����ăJ�N���N�}�m�~�����܂����B�����ƑO�Ɉ�x������A�ꏊ�Ȃnj��߂����Ă��܂������A���܂��ܐ^���ʂ肩����܂����B

�������E�E�E�B
�̌��ł��g���������E�E�E�B
���P�P�^�P�V�@�܂�̂����ꂽ�܂ɏ��J�@�C���@�Q�T���@�����@�Q�S�`�Q�T���@������k���@�g���Q�D�T�`�T�D�O�l�@�����x�@�P�`�T�l
�����B������A���₢��A��ӂ���~�葱�����J�͐���C�͂��ނ�������̂ɏ\���ȉJ�ʂ��������A���ɂȂ��ăL�����Z���̓d�b�ł����Ă��邩�ȁH�@�Ǝv���Ă������A���q�l�̃n�[�g�͋��������B�����ɂR�{�������Ă��܂����B
�C���ł̓E�~�E�V��������A�����Ȃ�������T���ĉE���������Ă��܂����B�܂��͂��q�l���������R�g�q���E�~�E�V�ł��B

���[��E�E�E�B�����c�m�N���~�h���K�C�ł��傤�B

���̃E�~�E�V�͂悭���O���킩��܂���B�܂��ɂȂƂ��ɒT���܂��ˁB

���q�l���������n�i�q�Q�E�c�{�����B����ȃ|�C���g�ŏo���Ƃ́E�E�E�B

�V���~�m�E�~�E�V���������E�E�E�A

���[��E�E�E�B�Ȃ�H�@�����͔����E�~�E�V�������āA���������������P�Z���`���邩�Ȃ����H�@���Ă��炢�̃T�C�Y�ł����B�݂�Ȃ܂��q���Ȃ�ł��ˁ[�B���ꂩ��~�Ɍ����Đ������Ă����āA�E�~�E�V�V�[�Y���X�^�[�g�ɂȂ�킯�ł��ȁB

�A�J�{�V�E�~�E�V���Ǝv���Ă�������ǁA�ȂႤ�悤�ȁE�E�E�B�L�k�n�_�E�~�E�V�������Ă��Ƃɂ��Ƃ��܂��B

�N�`�i�V�C���E�~�E�V���q���T�C�Y�ł����B

�Z�O���w�r�M���|���ΐF�̊C���̏�ɂ��܂����B���q�l�͎��T���S�̏�Ńi�C���|�[�Y�̌̂��B�e���Ă��������܂����B�����͂��q�l���E�~�E�V���B�e���Ă���Ԃɓ����Ă����܂��āA���q�l�ɂ͏Љ�Ă���܂���B����܂��[��E�E�E�B

�������A�J�{�V�E�~�E�V�Ȃ̂��ȁH

�g�K�����G�r�������ƁATozeuma lanceolatum �͌p�����Č����Ă��܂��B

�����ēD�n�̃W���[���ƃJ�G���A�}�_�C�ł��B���̑傫���̂͑S�R�����Ȃ��B�B��Ă������ɏo�Ă��Ă���܂��B�������̖ڃ����Y�ŎB���Ă��������B

�����������������E�E�B�A�J�G�r�̒��Ԃ��ȁE�E�E�B

�u�h�E�K�C�Ȃ̒��Ԃ�

���܂����B�����Đ�������̂Ƃقړ����ꏊ�ł܂������܂����B�E�i�M�M���|�ł��B���͋v���Ԃ�̏o��ł��B�ł��q���Ȃ̂ŁA�����ɉB����Ă��܂��܂��B

�P�V���E�n�[�̃I�X�͂���ς��Y��B�q���Ȃ�čL����ꂽ�����ς�~�܂��Č��Ă��܂��̂��B

�R�}�`�R�V�I���G�r���Ǝv���܂������A�t�^�X�W�E�~�V�_�R�V�I���G�r���Ǝv���܂��B

�����ă~�W�������ƃ��N�V�}�C���V�̌Q�ꂪ����ɐ��ʋ߂���p�j���Ă��܂����B

�n�i�~�m�J�T�S���A�^�b�N�I�I

���C�h�ŎB�肽������ǁA���͑����Ă��邵�E�E�E�A���邵���Ȃ����[�Ƃ������i�ł����B

�����͂����Ɨ₦���ނ����ł��B�|���ˁ[�B
���P�P�^�P�U�@�܂肽�܂ɏ��J�@�C���@�Q�T���@�����@�Q�S�`�Q�T���@�����琼���@�g���Q�D�T�l�@�����x�@�P�T�l
���s�[�^�[�̂��q�l�ƃ}���c�[�Ń_�C�r���O�B���C�ɂR�{�����Ă��܂����B
�܂��̓Z�I���[�ǂ���A�[���ق���T���B
����ƃN���X�W�M���|�����������o���Ă��܂����B���̖ڃ����Y�Ŋ���Ă��܂����B�����̂��q�l�͎B�肾�����炠�܂蓮���Ȃ��̂ŁA�������̖ڃ����Y�łƂ��Ƃ�B���Ă݂܂����B

�N�}�m�~�����͂��킢���B��܂����B

�I�j�J�T�S�̂悤�ɓ����Ȃ����ɂ���������n���B���������Y�����ɐG��邮�炢��ʑ̂ɂ͐ڋ߂��Ă��܂��̂ŁA�I�j�J�T�S���瓦���o���Ă��܂��܂��B

�I�����E�[�^���N���u�ɂ����Ċ��̂��B

�i�f�V�R�J�N���G�r�ɂ����̂��B
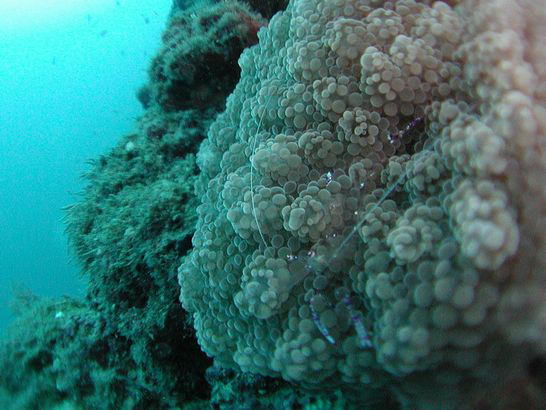
�j���̓C�\�M���`���N�̐X����`�����Ă��邩�̂悤�ɁE�E�E�B

�R�_�}�E�T�M�K�C�ɂ�����Ă��܂����B
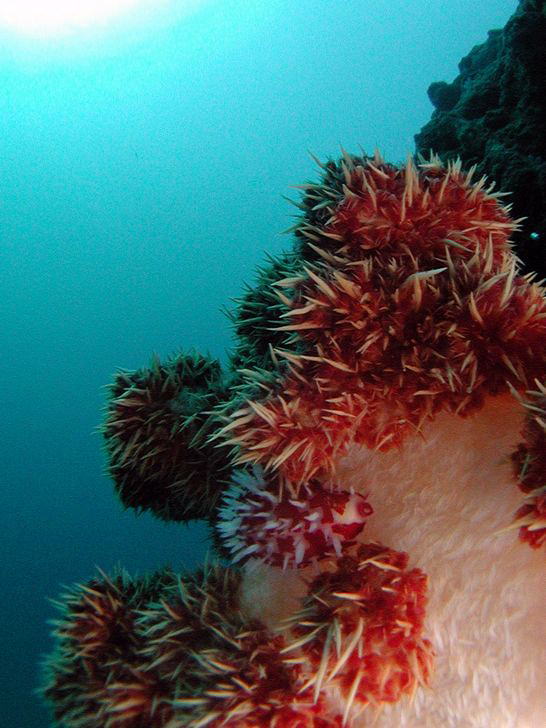
�C�\�o�i�ɕt�������S�~�̂悤�Ȓ�����G�r���o�Ă��܂����B�Ȃɂ�H

���܂蓦���Ȃ��W���[�ɂ��o��܂����B�������傫�������B�����鏬�����W���[�͂������܂����B

�ꏊ�ɂ���J�N���N�}�m�~�͎B��ɂ��������E�E�E�B�����̎ʐ^�̎R��z���܂����B���ꂾ���đS�R��]�ʂ�ɂ͎B��Ă��܂��A���ɂȂ��̂ōڂ��Ă��܂����B

�����Ē�Ԃ̃����c�L�J�G���E�I�B����͕��ʂ̃����Y�ŎB��܂����B

���J���ς���V��ł������Ȃ�Ƃ��R�{����܂�����B
���P�P�^�P�T�@�܂�̂�����@�C���@�Q�S���@�����@�Q�S�`�Q�T���@�k�����@�g���R�D�O�`�Q�D�T�l�@�����x�@�P�`�U�l
�v���Ԃ�E�E�E�Ƃ͂����Ȃ���T���V�тɗ��Ă������������q�l���J�����������čĖK���Ă���܂����B�������肢���Ă݂܂��傤�B
�L�k�n�_�E�~�E�V�����ɂȂ�̂��ȁE�E�E�B

�^�}�K���]�E�r�������A�������͂��̒��Ԃ����܂����B���̒��Ԃ����ނ��x��Ă��Ĕ��ʂ���������ł����A����Ȃ��Ƃɋ����̂��邨�q�l�͊F���Ȃ̂ŁA�^�}�K���]�E�r�����̒��ԂƂ������Ƃŏ\�Ȃ̂ł��B
![�^�}�K���]�E�r����](images/DSCNb92301.jpg)
�}�_���C���E�~�E�V�ɂ͒��̖ڃ����Y�Ŋ���Ă��܂����B�w�i�Ƀ_���_���_�e�n�[���B�e���邨�q�l����荞�߂܂����B

�J�C�����\�E�����Ԃ��Ă���V�J�N�C�\�J�����ɂ�����Ă݂܂������A��͂肻���ی�����Ă��܂��̂��B

�j�W�M���|�͂Ȃ��Ȃ��V�ׂ܂����B

�g�E�A�J�N�}�m�~�̐Ԃ����͓����Ă��܂��āA�Ȃ��Ȃ��ꏏ�ɗV�ׂ܂���ł����B

�V�}�M���|�Ƃ͂����ƗV�т��������E�E�E�B

���q�l�̂P�l�͍����͂P�{�ɂďI������܂����B�����͂������������x���A�b�v��������̂ɂȁ[�B
���P�P�^�P�S�@�܂�̂�����@�C���@�Q�U���@�����@�Q�S�`�Q�T���@�k���@�g���S�D�O�l�@�����x�@�R�`�U�l
�X�s�b�c�����߂ĖK��Ă��������邨�q�l�Ƃ̃}���c�[�_�C�u�ƂȂ�܂����B���������V�тɗ��Ă����������̂����A�C�͍r��Ă��܂��āA�|�C���g�I���ɂ͂Ȃ��Ȃ�����C���ł����B
���ǁA�܂��[�}���c�[�}�������A�ǂ��ł��V�ׂ�قǂ��q�l�̃��x�������������̂ŁA�D�܂݂�R�[�X�Ń|�C���g�𑊒k���Ȃ��猈�肵�V��ł܂���܂����B�����Ă����̂����A����͐�̓p�X���Ă��ƂŁA�C�ŗV�Ԃ��Ƃɂ��܂����B�r��ĊC�ł��˂�Ɛ키������ɓ������ق����y�����������Ă���Ǝv���̂��B
�q���n�[�̒��Ԃ����܂����B�����Ɣw�тꂪ�ʂ�܂ŔS���ĎB��Ȃ��Ɣ��ʂ͓�����A���̎�̋��Ɏ��Ԃ���������قǃK�C�h���͉ɂł͂Ȃ��̂ł���Ȏʐ^�����c��Ȃ��̂͂��傤���Ȃ��̂��B

�_���͂����ł����B�n�S�����n�[�B�ʐ^�̓I�X�ł��B�Y��ł���B

�I�C�����n�[����������܂��B

�N���I�r�n�[�͂��������傫�ڂ̌̂��K���K���o�Ă����̂ŁA���̖ڃ����Y�Ŋ���Ă݂܂������A���ɎB��Ȃ��E�E�E�B

�V�}�M���|�͂����ƗL���ɂȂ��Ăق������i���o�[�����ł��B

�T�U�i�~�t�O�q���ɂ͂�������o��܂����B

�C�b�|���e�O���̐����B������̓��X�̌̂ł��B

�J���X�L�Z���^�������̂ł����������̖ڃ����Y�ŎB���Ă݂܂����B

�K���X�E�V�m�V�^�����̖ڃ����Y�ŁB���Ȃ݂ɂ��̋��̃T�C�Y�͂Q�Z���`���炢�ł��B

���낢�����܂����B���q�l���y����ł����������悤�ʼn����ł����B�܂��̂��z�������҂����Ă��܁[���B
���P�P�^�P�R�@�J�@�C���@�Q�T���@�����@�Q�S�`�Q�T���@������k���@�g���S�D�O�l�@�����x�@�T�`�W�l
�Ȃ��Ȃ������C���Ȃ��A�������C���ŃX�s�b�c���߂Ă̂��q�l�ƃ}���c�[�}���_�C�r���O�B�����̗\��ł͒��ꂩ��̃_�C�r���O�ł������A�d�����������Ƃ̂��ƂŌߌォ��ɂȂ�܂����B
�ŁA�X�s�b�c�̋߂��ɂČߌォ���{�����Ă��܂����B�܂��̓C�\�J�N���G�r�����ɒ���B

�V�}�I���n�[�͓x���̂���n�[�Ȃ̂ŁA���̋G�߂ɒ��킵�Ă����Ȃ�V�ׂ܂��B

�n�S�����n�[�����͂��̋G�߂�������t�H�g�W�F�j�b�N�ȋ������A���̕q�����͉ď�̔�ł͂Ȃ��E�E�B�����B��Ă��܂��B���̎ʐ^�͕ʂ̓��ɎB�e�������̂��g���Ă��܂��B

�q�����V�̒��Ԃ��Ǝv���邪�A�����Ȃ̂ŎB���Ă݂܂����B

������Ɗ������E�~�E�V�B�N�����h�[���X�E�q���g�D�A�l���V�X�B

���R���ꂮ�炢�̑傫��������Β��̖ڃ����Y�ŎB���Ă݂����B���[��E�E�E�B���ɎB��Ȃ��ȁE�E�E�B

�R�����E�~�E�V�����܂����B

�����ă~�W���������o��B�}�N���[�Ȃ��q�l�͈�˂��Ă��܂苻���Ȃ������ł����B

�c�ʒu�ŎB���Ă݂�ƌQ��̌������悭�킩��܂���ˁB���̌��z���̓��b�h�r�[�`�̉��ɂ���S���ł��B
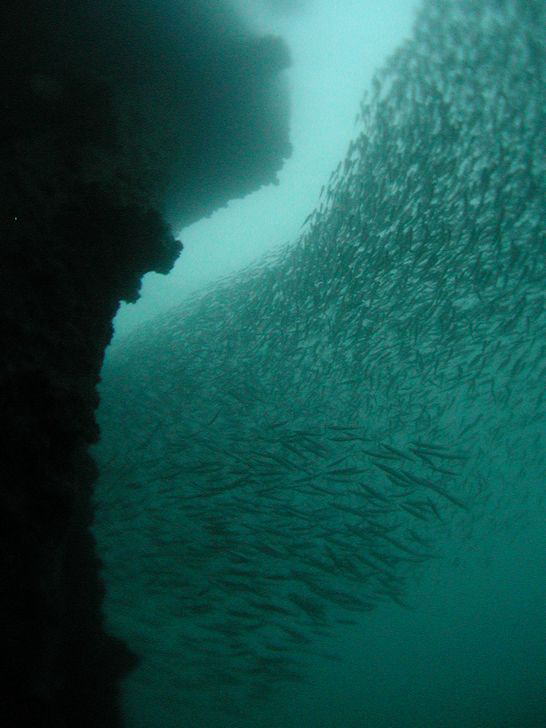
���̃~�W�����̌Q��A���܂ł���̂��ȁ[�H
���P�P�^�X�@����@�C���@�Q�V���@�����@�Q�T���@�쓌���@�g���Q�D�O�l�@�����x�@�P�T�`�Q�O�l
���s�[�^�[����Ђ̗��s�ʼn���ɗ����Ă��܂��āA�����������Ԃ��ł������Ă��ƂŐ���ɂ����܂����B���i�̓o���o���̃J�����h�̏���������ǁA����̓J�������Ȃ����Ă��ƂŁA��r�I�����x�̗ǂ��|�C���g�ł̂�Ђ蕗�i�Ȃǂ��y���݂Ȃ�������Ă��܂����B
���̓R���f�W�����Q���Đ����Ă����̂����A�������~�܂��ăo�V�o�V�B�e����킯�ɂ������Ȃ��̂ŁA�����قƂ�ǎB���Ă��܂���B�����炱���Ɏʐ^�͂Ȃ��B
���̖ڃ����Y���g���ēK���ɉ������B�����̂����A���̃����Y�͎�u�����₷���悤�ŁA�S�����ɎB��Ă��܂���ł����B�c�O�B
�_�C�r���O�ł͓����x�̗ǂ��C�Ō��C�Ɉ���Ă���T���S�̏���ړ��B�r���ɉ��C���̃I�j�q�g�f�����쏜����B�ŋ߂ł̓I�j�q�g�f�͈��҈�������ł͂Ȃ��A�ǂ��ʂ�����Ă���BYOMIURI ONLINE�x�Ɂu�I�j�q�g�f�Ń}�_�C���������E�E�E�S�t���X�g���X�ɘa�v�i�V���P�Q���j�Ƃ����A���Q��w��\���Y�����Z���^�[�̋L��������ł��B�����ȂƂ���ŕ���Ă���̂ł����m�̕��������ł��傤�B
�T���S�ʂ�H���r�炷���ҁA�u�I�j�q�g�f�v�����傷��S�t�ɁA���̐����𑣐i���鐬�����܂܂�Ă��邱�Ƃ��A���Q��w��\���Y�����Z���^�[�̎O�Y�ҋ����i���Y���������w�j��̃`�[���̌����ł킩�����B
�@�{�B���̃X�g���X���ɘa��������ʂ�����Ƃ݂���B���Z���^�[�͗{�B���Ƃւ̊��p�����҂ł���Ƃ��āA�����̓����i�߂�B
�@�����̂��������́A��N�P�O���A�T���S�ʕی�̂��߈��Q�����쒬���ߊl�����I�j�q�g�f���A���R�}�_�C�Ɠ��������ɓ��ꂽ�Ƃ���A�}�_�C���ʏ�������������邱�ƂɒS���҂��C�Â��A��������̎������n�߂��B
�@�}�_�C�̒t���P�T�C���j���P�g�������ɁA�I�j�q�g�f�P�O�L������ꂽ���̂ƁA����Ă��Ȃ����̂��R�T�Ԕ�r�����Ƃ���A�I�j�q�g�f�������������̃}�_�C�́A����Ă��Ȃ��}�_�C�����a���R�������H�ׁA�̒��̐L�т͂Q�{�ȏ�ɂȂ����B
�@����ɁA���t�͔������̔\�͂����܂�A�{�B�}�_�C�̑�ʎ��ɂȂ���a�C�̔��_�a���}�����ꂽ�Ƃ����B�S�t���}�_�C�̉a�ɍ����Ă��A�������ʂ�����ꂽ�B
�@�Ɖu�͂̌���̓q�����ł��m�F���ꂽ�Ƃ����B
�@�����Z���^�[�ɂ��ƁA�S�t�ɂ́A���Ƀ����b�N�X���ʂ�^���鐬�����܂܂�Ă���炵���B�O�Y�����́u�L���ȕ�������肵�Ď����ɉ�����A�{�B���Ƃ��������ł���v�ƃI�j�q�g�f�̌��p�Ɋ��҂���B
�@�I�j�q�g�f�́A�ő�Œ��a�U�O�Z���`���x�܂Ő�������T���S�̓V�G�B�ɐB�͂������A�j�ɖғł����邽�ߋ쏜�͗e�Ղł͂Ȃ��B
���̔S�t���ā[�̂��ǂ���w���Ă���̂��킩��Ȃ��̂����A�T���S��H�ׂĂ���Ƃ�������͂����Ƃ��ɃT���S�ɂ������Ă�����̂��낤���H�@
�܂��[�I�j�q�g�f���������̎��R���Ԍn�̈ꕔ�ő������ɗǂ��e����^���Ă��邱�Ƃ��킩������A����ύň��̐������Ă��[�̂͐l�ԂɂȂ�낤�ˁB
�����̂��q�l�͗��T�ɂ������V�тɗ��Ă��������܂��B���̂Ƃ��������݂����ȃy�^�€�ɂȂ邱�Ƃ��F��܂��傤�B
���P�P�^�W�@����@�C���@�Q�V���@�����@�Q�T���@������쓌���@�g���Q�D�O�l�@�����x�@�P�T�`�Q�O�l
�����̏o���͂��Ƒ��������B�ŋ߂͂U�����߂��Ȃ��Ɩ邪�����Ă��Ȃ��ł��B���X�Ɍ������ԓ����璩�Ă����Y�킾�����̂ŎB���Ă݂��B
�Ăɂ���������̒��Ă�����������Ǔ~�ɂȂ��Ă��������Y��Ȓ��Ă�����������邱�Ƃł��傤�B

�C�ł͐Ƀn�i�~�m�J�T�S�������Ă����B�C���V�̒t�����K�Q��Ă��āA������ǂ������Ă��܂����B�T�`�U�̂͂��܂������ˁE�E�E�B

�[��ł��q�l���X�~���i�K�n�i�_�C�Ɗi�����A���͑_���Ă����l�^��T���ɍs�����̂��������Ȃ��������Ă��܂����̂ŁA���q�l�̂�����Ə�ŃV���f�����E�~�E�V�Ȃ��B�e�B���[������ʑ̂������̖ڃ����Y�ŎB�e���Ȃ���E�E�E���Ă��ƂŁA����Ă��܂����B�G�o�Ƀs���g���������A���C�h�ɔw�i���u���[�Ő����E�E�E�B�ӂނӂށB

���̖ڃ����Y���ۂ��ʐ^���B��܂��ˁ[�B�߂��ɂ�������������߂ĎB���Ă݂܂����B

�����[�������E�E�E�Ǝv���ĎB�e���Ă����̂����A�ʐ^�Ŋg�債�Ă悭������`�S�~�m�E�~�E�V�ł����B�ӁA�ӂ��[�������B

���[�ƁE�E�E�E�B�J�T�S�̒��Ԃ̎q���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł�����ǁE�E�E�A�I�j�J�T�S���ǂ����͂��Ƃ킩��Ȃ��E�E�E�B

�ȑO�����I�I�����J�G���A���R�E�B���Ȃ�ړ����Ă��܂����B���̃_�C�o�[�������ČQ�����Ă����Ƃ�������ő҂��Ă��āA���Ă��܂����B

�N�}�m�~�ŗV��E�E�E�A

�ł̓g���V�r�C�g�q�L�x���ƋY�ꂽ��A

�J�~�\���E�I�������o������E�E�E�A

�������Ǝv���A�܂�����Ȃɂ��킢���n�}�N�}�m�~�̎q���������܂��B

�S�C�V�M���|�����܂����B

�����ė[�����Y��ł�����[�B

���P�P�^�V�@����@�C���@�Q�U���@�����@�Q�T���@�����@�g���Q�D�O�l�@�����x�@�P�T�`�Q�O�l
�n���̃��s�[�^�[�̂��q�l�ƌߌォ������Ă��܂����B�v���Ԃ�ɐ[��ɍ~��Ă݂�ƃz�^�e�c�m�n�[���o�Ă��܂����B
�w�тꂪ�ڂ�ڂ�Ō���������������قǂ̌����J���Ă��܂����B

���܂�B��Ȃ������̂ŁA���q�l���B�e������A���̖ڃ����Y�Ŋ���Ă݂��E�E�E�E���A���O�ɉB����܂����B

�p���_�_���}�n�[�����₷���ʒu�ɁB

���h�J���E�E�E�B

���̖ڃ����Y�Ŋ���Ă݂Ă��E�E�E�A�����������E�E�E�B

���̖ڃ����Y�������܂܃��C�h�Ȋ����ɃO���N�����B���Ă݂܂����B

�g���V�r�C�g�q�L�x���A�Љ�₷���̂ł��Љ�Ă��܂��B

�j���C�J�T�S���ȁH

�q�b�|���e�E�R�����T���X�����܂����B

�}���N�`�q���W���ȁH�@�}�ӂ̂悤�ȉ��F�����_���Ȃ�����ǁE�E�E�B

�L�x���N���X�W�E�~�E�V�ł��傤���ˁE�E�E�B

�N�r�A�J�n�[�����܂����B

�K���K�[�G�r�͑傫�������ł��B�y�A�ł��܂����B

�q�o�V���E�W�͎B��Ƃ�������Ȋ����ɂ����B��܂���B

�I�j�J�T�S�𒎂̖ڃ����Y�Ŋ���Ă݂��B

�S�̓I�ɋ������̎q�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�ނނށA�߂����B�܂��[�P�P���������傤���Ȃ�����ǂˁB
���P�P�^�Q�@����@�C���@�Q�R���@�����@�Q�T���@�k���@�g���S�D�O�`�T�D�O�l�@�����x�@�T�`�U�l
�S���I�Ȋ��g�̓����ɉ��ꂾ���ė₦����ł��܂����B�k�����ƂĂ������B����ȓ��͐��C�݂͑�r��B�䕗�Q�O���̂Ƃ������f�R�r��Ă���B�݂�Ȃ��ڎw���͓̂~�̃|�C���g�B����đ�W���ɂȂ��Ă��܂��܂����B
���R�ƕ��ԃo���̐����X�����B����ȓ����x�̈����|�C���g�ɂT�O�����炢�̓_�C�o�[�������Ă����Ǝv���B����A�����Ƃ��ȁE�E�E�B
���C�`�ŃX�s�b�c�̓G���g���[�����̂����A�P�{�ڂ̓����x�͂Ȃ��Ȃ��ǂ������ł���B

�傫�ȃJ���C�̒��Ԃ����܂����B

��̃A�b�v�͂���Ȋ����B

�ނނށE�E�E�B�ȑO�Ɍ������Ƃ��邼�B�J���C�̒��Ԃ��������ȁH�@�ƌ���ł͏Љ������ǁA�����̂g�o��k���Ē��ׂ���A�K���X�E�V�m�V�^�Ƃ������O���o�Ă����B��x�ڂ̏o������A���̋��̑�l�͌������Ƃ��Ȃ��B��x����Ă݂������̂��B

�i�K�Z�n�[�����܂����B�������D�n����Ȃ��B������ƍ��������邮�炢�̏ꏊ�ɁB���܂ł���̂��E�E�E�E�B

���[��E�E�E�B�܂����ׂ܂��B

������̓X�J�V�n�i�K�T�E�~�E�V���Ǝv���܂��B���͏����B��Ȍ`�̃E�~�E�V�ł����B

���q�ɏ���Ă����ꖇ�B

�L�k�n�_�E�~�E�V���������܂����B

���ɂ��F�X���Ă��܂����B�W���[�t�B�b�V���͐G��邮�炢�̌̂��������A�D�n�[�͂ЂƂƂ���A�V�}�I���A�J�X���A�N�T�A�N���I�r�A���c�V�A�t�^�z�V�^�J�m�n�A�n�`�}�L�A�j���E�h�E�A�n�S�����n�[�����ƌ��Ă��܂����B�V�}�M���|�A���G���}�M���|�A���C�g�M���|�A�j�W�M���|�A�p���_�_���}�n�[�A�_���}�n�[�A�t�^�C���T���S�n�[�A�R���_�C�����A�C�\�J�N���G�r�����A�j�Z�A�J�z�V�J�N���G�r�A�J�U���C�\�M���`���N�G�r�A���R�V�}�G�r�A�N���A�N���[�i�[�V�������v�A�C�\�o�i�K�j�A�C�\�o�i�J�N���G�r�A�A�J�X�W�J�N���G�r�ȂǂȂǁE�E�E�B
���P�P�^�P�@����̂��ɑ�r��@�C���@�Q�V���@�����@�Q�U���@�쓌����k���@�g���R�D�O�l�@�����x�@�P�T�`�Q�O�l
�����H�@���Ă��炢�����V�C�ɂȂ��Ă��܂����B���q�l�̓�����̍s���̑f���炵���ł��낤�B�P�P���Ƃ͎v���Ȃ��قǂ̉����ƃx�^�€�B
�f���炵���E�E�E�B
����ȃR���f�B�V�����̒��A�i�J���g�C�����P�n�[�����������������Ƃ������N�G�X�g�����������Č��Ă��܂����B�܂��܂����������܂�����B�������ƕq���ɂ͂Ȃ��Ă��܂����B
���ɂ̓Z���e���C���E�~�E�V�̐F�o�[�W������A�C�\�M���`���N���h�L�J�N���G�r�A���L���R�{�E�V�K�j�Ȃǂ����Ă��܂����B

�����ċv���Ԃ�Ɍ����n�_�J�R�P�M���|�B

�q���z�\�E�~���b�R���ȁE�E�E�B���q�l�ɂ̓n�N�e�����E�W���ȁE�E�E�Ə����Ă��܂����B�������Ƃ��Ă��������܂��B

�����ăI�L�i���n�[���ȁH�@�Ǝv���Ă������̋��́E�E�E�E�A��������炸���O���킩��Ȃ��B�ł��I�L�i���n�[�̒��Ԃł͂Ȃ������ł��B

�[�j�K�^�t�V�G���K�C���Y��Ȍ̂ł����B

�z�^�e�E�~�w�r�͑S���łS�́B���̖ڃ����Y�Ŋ���Ă݂܂����B

���̌`���ό`���Ă���z�����܂��āA����āA���̖ڃ����Y�ŎB���Ă݂��B����ʂ��Ă��邨�q�l�܂Ŏʂ肱�ށB�����Y�͂قڃz�^�e�E�~�w�r�ɂ������Ă���悤�ȎB�e�����ł��B

�[���A�G�L�W�b�g�̎��ɂ͂��łɊC�͍r��Ă����B�V�C�\����Ȃ������E�E�B
���P�O�^�R�P�@�܂肻���Đ���@�C���@�Q�T���@�����@�Q�U���@�k�����@�g���P�D�T�l�@�����x�@�Q�O�l
��������O���ԑ����Đ����Ă��������邲�v�w�̏����B�K���C�����₩�ɂȂ��ĂȂ��Ȃ����������B
�ߌォ��P�l�A�Q�l�Ɛl���������čŌ�͂S���Ő����Ă��܂����B
�v���Ԃ�̃|�C���g�������̂ŁA�l�^��T���Ȃ���̃_�C�r���O�������̂ŁA���炾������Ă��܂����B
�Z�O���w�r�M���|���ȁE�E�E�B

�m�R�M���n�M�������F�ɂȂ��Ă��܂����B

���ܔw�т�S�J�Ŏ��͂́E�E�E�A���͂́E�E�E�E�B

���[��E�E�E�A�܂��ɂ���݂̂͂�ȃV�}�L���`���N�t�O�Ȃ�ˁB�Ȃɂ��v���Ĕނ�ɃA�s�[�����Ă����̂��낤���H�@���Ȃ蒷�����ԃA�s�[�����Ă��܂�����B

���ɂ̓q���I�j�n�[�A�q���i�K�l�W�����{�E�A���m�_�e�n�[�A�_���_���_�e�n�[�A�����O�A�C�W���[�A�s�O�~�[�V�[�h���S���A�x�j�q���C�g�q�L�x���A�o�u���R�[�����V�������v�A�����C���h���G�r�A�p���_�_���}�n�[�A�J�T�C�_���}�n�[�A�C�\�M���`���N�G�r�A�q�b�|���e�E�R�����T���X�Ȃǂ����Ă��܂����B
���P�O�^�R�O�@����@�C���@�Q�U���@�����@�Q�U���@�k�����@�g���P�D�T�l�@�����x�@�Q�O�l
�ĂɗV�тɗ��Ă������ǂ���������������ɗ��Ă���܂����B���͍���͂�������̐V���������Y�Ŏ����B������˂Đ����Ă��܂����B
�[��ł̓q���I�j�n�[���B

�x�j�q���C�g�q�L�x���̎q���͐K�����ق�̂�g�F�ɕς���Ă����̂����܂����B

�L���`���N�K�j�����B�悵�V���������Y�ŎB���Ă݂悤�B�����������Ɋ��邯��ǃ��C�h�B���[�����ʐ^���B��܂��B�L���`���N�K�j�̖ڂ܂ŎB��Ă��邯��ǁA���̃_�C�o�[�̃t�B���܂Ŏʂ��Ă���B�y�����\�}���B

�o�u���R�[�����V�������v�ɂ�����Ă݂����A�Ȃ��Ȃ��Ӑ}�����\�}�ɂ͏o���Ȃ������B�܂��܂��o����ς܂Ȃ��ƁE�E�E�B
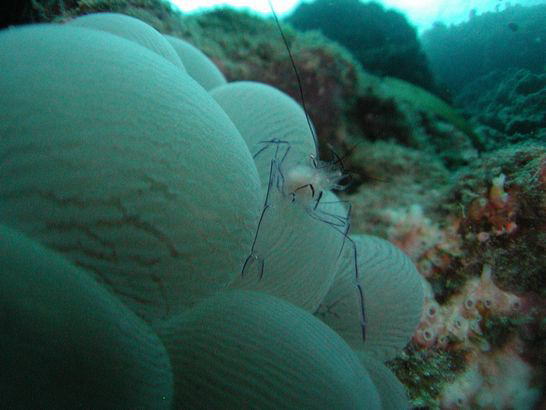
�N�}�m�~�ŗ��K�B����āA�����Ɗ���āB

�����Ɗ�肽�������E�E�E���A��������ƃs���g������ς�Ȃ��Ȃ������ɂ����B���K����݂̂��E�E�E�B�撣�낤�B

���P�O�^�Q�X�@����@�C���@�Q�U���@�����@�Q�U���@�k�����@�g���P�D�T�l�@�����x�@�Q�O�l
�C�w���s�̑̌��_�C�r���O�̂���`���ł����B
���P�O�^�Q�W�@����@�C���@�Q�U���@�����@�P�X�`�Q�O���@�k�����@
�Ȃɂ��\��̂Ȃ����ł������A�ߑO���ɓ��˂ɓd�b�ŗ\����܂����B�_�C�r���O�H�@�m���m���B�����B���o�[�g���b�L���O���B
����A�����B�������ˁB
�����̐�͑���킢�B��������̐l���V�тɗ��Ă��܂������A�E�F�b�g�X�[�c�𒅂Ă����͉̂�X�X�s�b�c�����B���݂̂Ȃ���͐����œ������Ă����̂����A�m���Ɋ������B�����͂P�X�`�Q�O�x�ł����B
����ł��݂�ȑ�ɑł���Ă��܂����B��ɂ͂��[�����p���[�������ł��傤�ˁB�݂�Ȃ��������荞�މ������B

�A�肪���̓��[�ō炢�Ă����n�C�r�X�J�X�B�썑�炵���Ԃł��ˁB

�V���m�Z���_���O�T�Ƃ����܂��B���̉Ԃ̓r�[�`�Ń_�C�r���O���ĂĂ������܂��B����ł͂������������ȂƂ���Ō����܂��B

���ЂP�P�������o�[�g���b�L���O�Ŋy���݂������̂ł��B�ɂȂ̂ŁA�݂�ȗ\�ĂˁB
���P�O�^�Q�V�@����@�C���@�Q�U���@�����@�Q�O���@�k�����@
�����̓��o�[�g���b�L���O�B���Ȃ�O����\�Ă��������Ă��āA�y���݂ɂ��Ă���ꂽ�Ƃ̂��ƁB�䕗�ʉߌ�̉���ł������A��͖��Ȃ��y���߂܂����B
��̐��͂��������₽���Ȃ��Ă��܂����̂ŁA��������X�[�c�𒅗p���ăg���b�L���O���Ă��܂����B��ɒ����܂ł͊������ɂȂ�܂����A�݂�Ȋy�������ɕ����Ă����B
��������Ƃ��̂��킟�[���Ċ����͉��x�����Ă���������ł��B
�����Ă�����������X�B��̐����Ԃ��𗁂тĂ��邾���ł��C����������ł��B

�A�H�͂������łɂ��ԔG��ɂȂ��Ă���̂ŁA��ɃW���u�W���u�����ėV�тȂ���A��܂��B

��ɓo������A��̐[�݂ɂт����肵����B�q���̍��ɂ͕p�ɂɑ̌����Ă����ł��낤���o�ł����A�ŋߑ�l�ɂȂ��Ă���͂Ƃ�Ƃ��������̂͂��B�݂�ȁA���������C�����ŗV�ׂ܂��B
�䕗��ł������A���ʂ́E�E�E�A�܂��[�������͑�����������ǁA�����[���[�����I�I�@���Ē��ł͂���܂���ł����B

�����ȑ�ڂɂ͊�̏ォ��_�@�@�@�@�@�C�u�b�I�I�@�E�F�b�g�X�[�c�𒅂Ă���̂œM���S�z���Ȃ��݂�Ȋy�������ɔ��ł܂�����B
�~�ł��S�R�V�ׂĊy�����̂��B

�䕗��߂̐���n��z�����ؘR����ƂȂ��Đ�ɒ����l�͎��ɔ������B�C�ɂ͂Ȃ��R�̑f���炵�����B
���Љ���̎R�Ɛ�ɂ��V�тɗ��Ă��������B

�Ō�͂����V�����[�𗁂тāA�����ւ��e���g�Œ��ւ����ĉ��U���܂����B